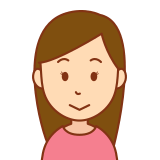
つみたてNISAって最近流行っててやったほうが良さそうな気もするけど、実際よくわからないし面倒くさそうだなぁ。
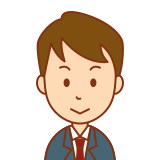
面倒くさいことは確かだけど、お金を貯めるのはそんなに楽じゃないことはみんな知っているはず。ここで分からないことを解決してインフレに負けない資産を築こう!
※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
つみたてNISAとは
そもそもつみたてNISAとはなんでしょうか。非課税?分散投資?長期積立? わからない単語がたくさん並んでますね。この記事をみて一つでも多く金融用語を覚えてあなた将来の生活をより豊かにしましょう。
つみたてNISAは、2018年に開始された少額投資非課税制度で、2024年に新NISAとして改正し、より柔軟かつ恒久的な制度となりました。主に長期積立・分散投資を目的とした投資信託が対象商品となっており、初心者でも始めやすい制度です。
つみたてNISAにはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類があります。それぞれ投資の限度枠があります。以下の表は生涯投資限度額や年間投資枠をまとめたものです。
| 項 目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 1200万円 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 月間投資枠 | 20万円 | ー |
表から分かるようにつみたてNISAを利用して非課税で資産運用出来るのは、1800万までです。これはお金持ちが無制限で税制優遇を受けられることを防ぐためです。
又、つみたてNISAは複利の効果が期待され、元金+運用益に金利がつくため早く始めればその分複利の恩恵を受けることになります。
つみたてNISAのメリット・デメリット
メリット
1 非課税の恩恵
通常株式や投資信託で得た利益は20.315%課税されます。つみたてNISAは全て非課税です。
2 少額から始めはられる
証券会社によって異なりますが、SBI証券や楽天証券では毎月100円から始められます。投資初心者だが興味はある、こういった人達にはもってこいの制度ですね。
3 インフレに対応出来る
株式や投資信託は一般にインフレ(物価上昇)に強いと言われています。理由は企業の売上や利益が増加することで、株価や配当金の上昇が期待出来るためです。
デメリット
1 元本割れのリスク
短期運用の場合、投資額が市場変動で下回る可能性が高く、元本割れのリスクが増します。ただし、20年以上の長期分散投資では、過去の実績から元本割れのリスクがほぼゼロになる傾向があります。
2 対象商品の制限
金融庁が指定した「投資信託」と「ETF」のみが対象です。これらは、積立・分散投資に適した商品に限定されています。
iDeCoとつみたてNISA何が違うの?
表にしてみたのでご覧ください。
| 特 徴 | iDeCo | つみたてNISA |
| 目 的 | 老後資金の積み立て | 自由な目的の資産形成 |
| 引き出し | 原則60歳まで不可 | いつでも可能 |
| 税制優遇 | 運用益非課税、所得税控除 | 運用益非課税 |
| 年間上限 | 職種によって違う(公務員の場合24万円) | 360万円 |
| 利用可能年齢 | 20歳以上~60歳未満 | 18歳以上 |
どっちから始めるべきですか?という声が聞こえてきそうですが、私個人の意見としては先につみたてNISAをはじめることをおすすめします。理由はつみたてNISAはいつでも引き出すことが可能であるからです。所得税控除がありiDeCoはコスパこそ最強なのですが、目的が老後資金ということもありすぐに引き出せないことが最大のデメリットです。
おすすめ証券会社
このサイトでは2社おすすめしています。
- SBI証券
- 楽天証券
なぜこの2社かというと、どちらも少額の100円から始められるなど、様々な理由があります。この内容は他の記事で書いているので参考にしてみてください。
まとめ
つみたてNISAは初心者から経験者まで幅広い層に適した仕組みとなっています。
ここまでメリット・デメリットを話してきましたが、あくまで投資は自己責任です。また、つみたてNISAは生活防衛資金を確保した上での余剰金でやるものです。将来の老後が不安だ、子どもに進学を諦めさせたくない、そんな想いがある方は適切なリスクヘッジを実施して、より豊かな人生を歩めるよう選択をしてください。



コメント