不動産を購入したとき、多くの方が見落としがちなのが「不動産取得税」です。この税金は新築・中古を問わず発生し、場合によっては数十万円の負担となることも。
しかし、軽減措置を適切に申請すれば最大で数十万円の節税が可能です。ただし、申請期限を過ぎると一切の軽減が受けられなくなるため、早めの対応が重要です。
この記事では、不動産取得税の軽減措置について、申請期限、必要書類、手続き方法を2025年最新情報に基づいて詳しく解説します。
この記事でわかること
- 不動産取得税軽減措置の対象条件
- 申請期限と手続きの流れ
- 必要書類と準備のポイント
- よくある失敗例と対策
- 都道府県別の違いと注意点
不動産取得税軽減措置の基本知識

軽減措置の対象となる不動産
不動産取得税の軽減措置は、以下の条件を満たす住宅用不動産が対象となります。
新築住宅の場合
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 自己居住用または家族の居住用
- 戸建て住宅・マンション問わず対象
中古住宅の場合
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 築年数:木造20年以内、耐火構造25年以内
- 耐震基準適合証明書があれば築年数制限なし
住宅用土地の場合
- 住宅と同時取得、または住宅取得から1年以内に取得
- 住宅の床面積の10倍まで(最大200㎡)
軽減措置による節税効果
軽減措置を受けることで、以下の控除が適用されます。
新築住宅
- 1,200万円を控除(認定長期優良住宅は1,300万円)
中古住宅
- 建築年に応じて100万円~1,200万円を控除
住宅用土地
- 45,000円または住宅1㎡あたり単価×住宅床面積×2×3%のいずれか高い方を控除
申請期限はいつまで?緊急チェックポイント

基本的な申請期限
原則:不動産取得から60日以内
ただし、都道府県によって期限が異なります:
- 東京都:取得から60日以内
- 大阪府:取得から6ヶ月以内
- 神奈川県:取得から20日以内
- 愛知県:取得から60日以内
期限を過ぎた場合のリスク
申請期限を過ぎると…。
- 軽減措置は完全に適用不可
- 固定資産評価額の3~4%を満額支払い
- 数十万円の節税機会を永久に失う
今すぐ確認すべきこと
□ 不動産取得日から何日経過しているか
□ お住まいの都道府県の申請期限
□ 必要書類の準備状況
□ 提出先の確認
必要書類と準備のポイント
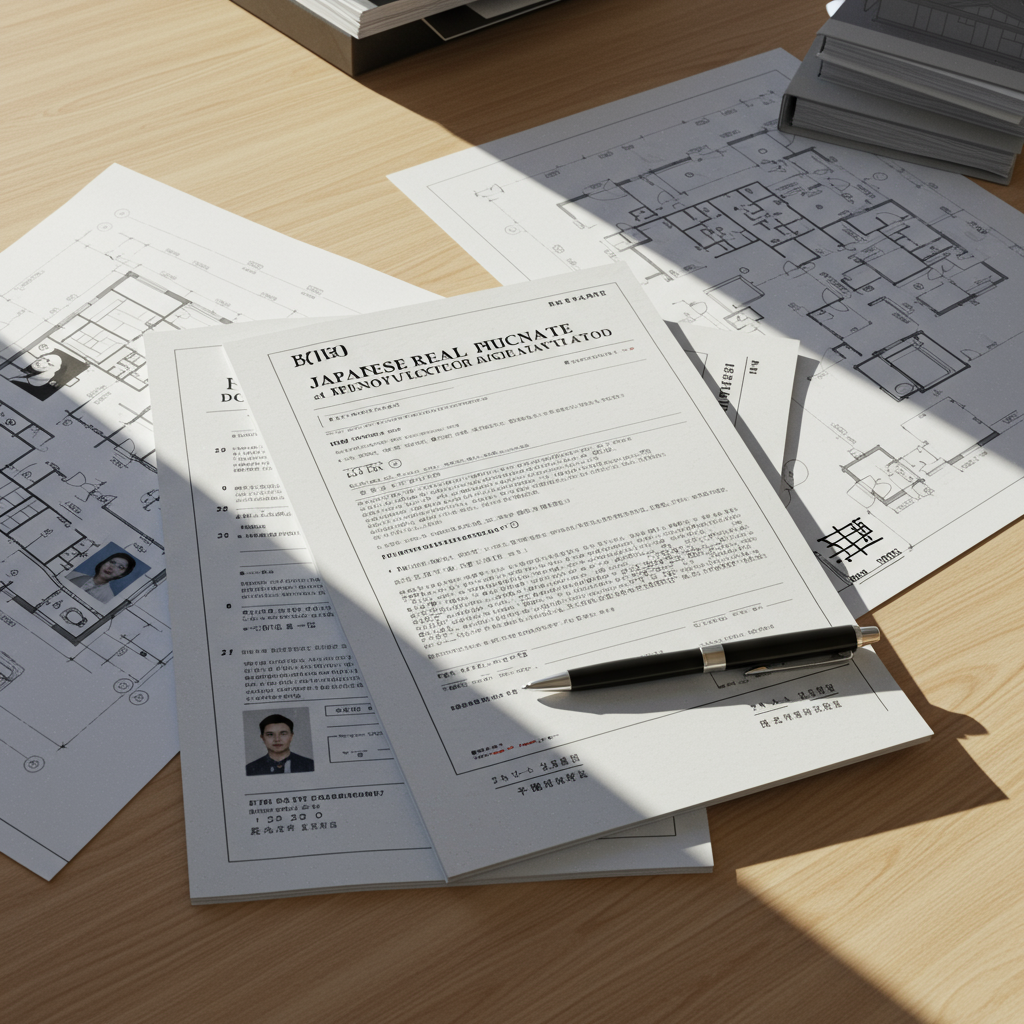
基本的な必要書類
共通して必要な書類
- 不動産取得税申告書(都道府県所定の様式)
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 住民票(居住実態の証明)
- 売買契約書または建築請負契約書の写し
- 住宅の平面図・配置図
中古住宅の場合の追加書類
- 耐震基準適合証明書(築年数超過の場合)
- 建築確認済証の写し
- 検査済証の写し
書類準備でよくある失敗
失敗例1:契約書のコピーに不備
- 全ページのコピーが必要
- 署名・押印部分も明確に
失敗例2:古い住民票を提出
- 取得後の住所変更が反映されていない
- 発行から3ヶ月以内のものを準備
失敗例3:耐震証明書の取得忘れ
- 中古住宅で築年数を超える場合は必須
- 取得に時間がかかるため早めの手配を
手続きの流れと提出先

申請手続きの基本的な流れ
Step1:必要書類の準備(取得後すぐ開始)
- 各書類の取得・準備
- 記入事項の確認
Step2:申請書の作成
- 都道府県指定の申請書に記入
- 添付書類の整理
Step3:提出
- 都道府県税事務所へ持参または郵送
- オンライン申請対応地域もあり
Step4:審査・決定
- 提出から1~2ヶ月で結果通知
- 軽減後の税額で再計算
都道府県別の提出先
東京都:都税事務所
大阪府:府税事務所
神奈川県:県税事務所
愛知県:県税事務所
※詳細な住所・連絡先は各都道府県のホームページで確認
オンライン申請の対応状況
2025年現在、以下の都道府県でオンライン申請が可能
- 東京都(一部手続き)
- 大阪府(電子申請システム)
- 神奈川県(e-kanagawa)
軽減措置を受けられないケース

対象外となる不動産
- 事業用不動産(店舗、オフィス等)
- 投資用不動産(賃貸目的)
- セカンドハウス(別荘等)
- 床面積が基準外(50㎡未満、240㎡超)
よくある勘違い
勘違い1:「購入=自動適用」
→ 申請手続きが必要
勘違い2:「税務署で手続き」
→ 都道府県の税事務所が窓口
勘違い3:「後からでも申請可能」
→ 期限厳守が絶対条件
2025年の制度変更点と注意事項

制度の継続性
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は2025年12月まで延長
- 不動産取得税の軽減措置も継続予定
- ただし、自治体ごとの条例で詳細は異なる
2025年の主な変更点
- デジタル化の推進
- オンライン申請対応自治体の拡大
- 必要書類の電子化対応
- 手続きの簡素化
- 一部書類の省略が可能に
- 申請書様式の統一化
よくある質問(FAQ)

Q1:申請期限を過ぎてしまった場合、救済措置はありますか?
A1:基本的に救済措置はありません。ただし、自然災害等の特別な事情がある場合は、各都道府県に個別相談することをおすすめします。
Q2:マンションと土地を別々に取得した場合はどうなりますか?
A2:マンションの場合、建物と土地の持分は一体として扱われるため、同時取得とみなされます。
Q3:軽減措置を受けた後に転売した場合、何か問題はありますか?
A3:軽減措置を受けた後の転売に制限はありませんが、居住実態がなかった場合は軽減措置が取り消される可能性があります。
Q4:親族から不動産を相続した場合も対象になりますか?
A4:相続による取得は不動産取得税の対象外のため、軽減措置の申請は不要です。
今すぐやるべきアクションプラン

緊急度別チェックリスト
【緊急】取得から30日以内の方
□ 居住地の都道府県税事務所に連絡
□ 申請期限の正確な確認
□ 必要書類リストの入手
□ 書類準備の開始
【至急】取得から30-50日の方
□ 必要書類の至急準備
□ 申請書の記入・提出準備
□ 提出方法(持参/郵送)の決定
【注意】取得から50日超の方
□ 即座に都道府県税事務所に相談
□ 期限延長の可能性確認
□ 緊急での書類準備・提出
書類準備の優先順位
優先度1:時間がかかる書類
- 耐震基準適合証明書
- 登記事項証明書
優先度2:役所関連書類
- 住民票
- 建築確認済証
優先度3:手元にある書類
- 売買契約書
- 平面図・配置図
まとめ:数十万円の節税を逃さないために

不動産取得税の軽減措置は、適切に申請すれば大幅な節税が可能な制度です。しかし、申請期限を過ぎると一切の軽減が受けられなくなるため、早急な対応が必要です。
重要ポイントの再確認
- 申請期限は原則60日以内(都道府県により異なる)
- 必要書類の準備には時間がかかる
- 提出先は都道府県の税事務所
- 期限を過ぎると救済措置はない
最後のチェック
不動産を取得した方は、以下を今すぐ確認してください。
□ 取得日からの経過日数
□ 居住地の申請期限
□ 必要書類の準備状況
□ 提出先の確認
期限が迫っている方は、今すぐ行動を開始しましょう。数十万円の節税機会を逃さないために、迷っている時間はありません。
軽減措置を活用して浮いた税金は、住宅ローンの繰上返済、家具・家電の購入、投資資金など、有効活用してより豊かな生活を実現してください。
あわせて読みたいこんな記事↓



コメント