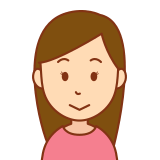
付加年金?なにそれやったほうがいいの?
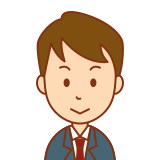
人によってやったほうがいい人とやらないほうがいい人がいるから記事の内容をしっかり理解して自分で決断していこう!
付加年金とは
付加年金とは毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして払い込むことで、将来的に受け取れる年金額に払い込んだ月数×200円の金額が加算される年金制度のことです。いったい何を言っているのかわからないと思いますので、一つ計算例をあげて説明します。
例:20歳から60歳まで付加年金に加入していた場合
プラスで払い込む保険料→400円×12か月×40年=192,000円
将来加算される年金受給額→200円×12か月×40年=9,600円
あれ半分に減っていないか?と思った方いるのではないでしょうか。これは年額9,600円増えるということなんです。つまり2年目でもとが取れ、それが亡くなるまで続くということです。月額にすれば800円ですが、老齢基礎年金の受給額が永久に増額されるので、老後生活のちょっとした足しになりますね。
加入できる期間は20歳〜60歳までで最大40年間。付加年金が受給されるのは老齢基礎年金と同じタイミングの65歳になってからです。また知らなくて納付期限を経過した場合でも期限日から起算して2年間までならさかのぼって納付が可能です。加入するのであればぜひ覚えておきましょう。
付加年金の加入条件
付加年金に加入できる人は国民年金第1号被保険者です。国民年金第1号被保険者とは20歳〜60歳未満の自営業やフリーランス、農家、学生、無職などです。
逆に加入できない人は第2号被保険者(会社員や公務員など)、第2号被保険者に扶養される家族である第3号被保険者です。また自分で国民年金基金に加入している方や国民年金保険料の免除や猶予を受けている人も加入できません。
会社員や公務員は老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せして受給できるため、付加年金で受給額を増やさなくてもいいでしょ!みたいなイメージですね。
付加年金のメリット
- 年金受給2年目以降から払った保険料のもとが取れる。
- 繰り下げ受給をした際は、同じ比率分給付年金も増額する。
- 付加年金として払い込んだ保険料は全額が所得控除の対象となる。
- 受給時、付加年金分は課税対象外(非課税)である。
受給金額が増える+税制優遇があるので、得られるメリットは大きいと思います。
付加年金のデメリット
- 65歳未満で亡くなった場合、付加年金保険料は返金されない。
- 65歳以上67歳未満で亡くなった場合、付加年金は受給できるがもとが取れない。
- 繰り上げ受給をした際は、同じ比率分給付年金も減少する。
- 付加年金加入中、納付を止めたい場合は付加保険料納付辞退申出書の提出が必要
- iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、拠出限度額が減額する。
iDeCo(個人型確定拠出年金)をやっている人は要注意です。自営業やフリーランスなどはiDeCoの月上限が68,000円なのですが、付加年金400円分が引かれてしまいます。つまり月67,600円になってしまいます。iDeCoの掛け金は1,000円単位なので月67,000円になってしまいます。
付加年金の加入方法
付加年金の加入手続きは、お住いの地域を管轄する市区町村役場や年金事務所の「保険年金課」まで行く必要があります。また、加入手続きを行うためには、以下の持ち物が必要です。
- 国民年金付加保険料納付申出書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
マイナンバーカードを持っていない場合には、個人番号入り住民票と本人確認書類を持っていけば申請が可能です。
委任状があれば誰かに手続きをお願いすることも可能です。
付加年金の保険料の納付は申し込んだ月の分からになります。付加保険料の納付期限は翌月末日までと決められているので、納付が遅れてしまうことのないように注意が必要です。
まとめ
付加年金とは毎月の国民年金保険料に上乗せして払い込むことで、将来的に受け取れる年金額が増額される年金制度のことです。老齢基礎年金の受給額が永久に増額されたり、払い込んだ付加年金の保険料は全額が所得控除の対象となるためメリットは以上に大きいです。その反面iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額を減少させてしまうなどのデメリットもありますので、この記事の内容をしっかり理解して自分がどうしていきたいのかを決めていきましょう。



コメント