「物価高で家計が苦しい」「政府の給付金はいつ、いくらもらえるの?」と不安を感じていませんか?
2025年現在、政府は物価高騰の影響を受けている世帯を支援するため、複数の給付金制度を実施・検討しています。
この記事では、現在進行中の給付金(住民税非課税世帯への3万円給付金)と、今後の検討状況(国民一律2万円給付金)について、専門家として最新情報を分かりやすく解説します。
支給時期や対象者、申請方法はもちろん、あなたの家計への具体的な影響まで、知りたい情報をすべて網羅しています。
この情報を活用し、賢く給付金を受け取り、あなたの家計を立て直す第一歩を踏み出しましょう!
この記事のポイント
- 住民税非課税世帯への3万円給付金は、既に多くの自治体で2025年1月〜3月頃から支給が始まっています。
- 18歳以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき追加で2万円が加算されます。
- 国民一律の2万円給付金は、まだ検討段階で支給時期は未定です。
- 支給時期や申請方法は自治体によって異なるため、お住まいの地域の最新情報を確認しましょう。
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
2025年最新:今もらえる給付金は?「いつ」「いくら」徹底解説
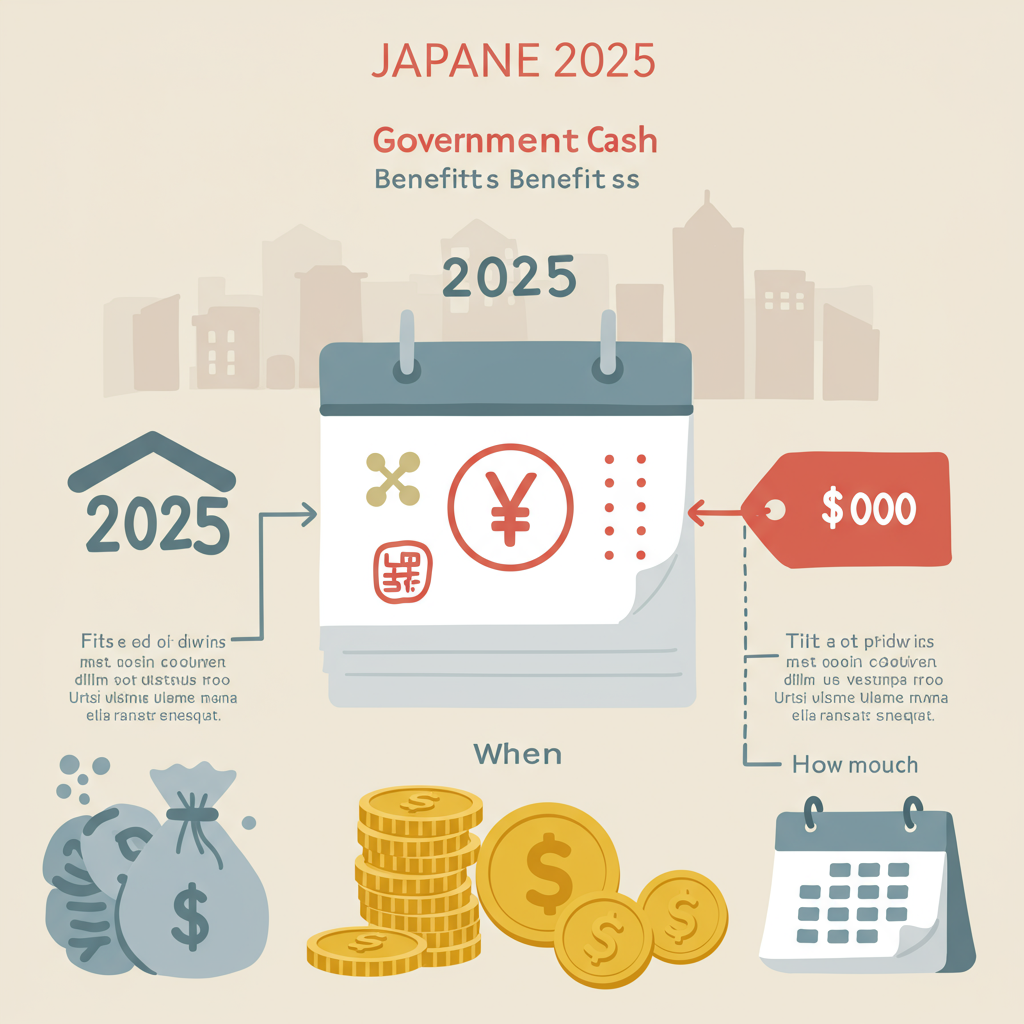
この章でわかること
- 住民税非課税世帯への3万円給付金の対象者と支給額
- 子ども加算の条件と金額
- 最新の支給時期と地域差
- 申請から受け取りまでの具体的な流れ
住民税非課税世帯への3万円給付金とは?
現在、最も広く実施されている給付金は、住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり3万円の給付金です。
この給付金は、2024年11月22日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、物価高騰の影響を特に大きく受けている低所得世帯を支援するために導入されました。
【対象者】
- 世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。
- 住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定基準以下であるため、住民税(均等割・所得割)が課税されない世帯を指します。基準は自治体によって若干異なりますが、おおむね単身世帯で年収100万円以下(給与収入のみの場合)が目安です。
- 2024年12月1日時点でその自治体に住民登録がある世帯が原則です。
支給額は?子どもがいる場合は追加加算も!
この住民税非課税世帯への3万円給付金の基本的な支給額は、1世帯あたり3万円です。
さらに、子育て世帯への支援として、以下の追加加算があります。
- 子ども加算:18歳以下(2006年4月2日生まれ以降)の子ども1人につき、追加で2万円が支給されます。
【支給額の例】
- 単身の住民税非課税世帯:3万円
- 夫婦のみの住民税非課税世帯:3万円
- 夫婦と子ども1人(18歳以下)の住民税非課税世帯:3万円 + 2万円 = 5万円
- 夫婦と子ども2人(ともに18歳以下)の住民税非課税世帯:3万円 + 2万円 + 2万円 = 7万円
この給付金は、生活保護受給者も対象となり、保護費の収入として認定されないため、保護費が減額されることはありません。
また、所得税や住民税もかからない非課税所得です。
いつもらえる?最新の支給時期と地域差
住民税非課税世帯への3万円給付金の支給時期は、自治体によって大きく異なります。
- 早い自治体では2025年1月から支給が開始されました。
- 多くの自治体では2025年2月~3月頃に支給が集中しています。
- 報道によると、約7割の自治体が3月までには支給を開始し、残りの約3割の自治体は4月以降の支給を予定しているとのことです。
支給が遅れる主な理由としては、対象世帯の抽出や確認作業、申請書の発送・受付、審査などに時間がかかることが挙げられます。
特に人口の多い都市部では、手続きに時間がかかる傾向にあります。
ご自身の住む自治体の正確な支給時期については、自治体の公式ウェブサイトや広報誌を必ず確認してください。
電話での問い合わせ窓口を設けている自治体も多いので、そちらも活用しましょう。
申請は必要?受け取りまでの具体的な流れ
この給付金は、基本的に申請が必要な場合と、申請が不要な場合(プッシュ型給付)があります。
【申請が不要なケース(プッシュ型給付)】
- 前回の類似の給付金(例:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)を住民税非課税世帯として受け取っており、かつ世帯状況に変化がない場合、自治体から「給付金のお知らせ」や「振込通知」が送られてくることがあります。
- この場合、原則として申請手続きは不要で、前回と同じ口座に自動的に振り込まれます。ただし、口座変更などを希望する場合は、別途手続きが必要です。
- 通知が届いたら、記載内容に間違いがないか必ず確認しましょう。
【申請が必要なケース】
- 初めて住民税非課税世帯となった場合。
- 世帯状況に変化があった場合(転入、婚姻、離婚、出産など)。
- 前回の給付金を受け取っていない場合。
- 自治体から「支給要件確認書」または「申請書」が届いた場合。
【申請から受け取りまでの一般的な流れ】
- 通知の確認:自治体から郵送される「給付金のお知らせ」「支給要件確認書」「申請書」などの書類を確認します。
- 内容の確認・記入:
- 「支給要件確認書」の場合:記載されている氏名や口座情報に間違いがないか確認し、チェック欄にチェックを入れて返送します。原則として添付書類は不要です。
- 「申請書」の場合:必要事項(氏名、住所、振込口座など)を記入し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写しなど)と口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)を添付して返送します。
- 返送/提出:指定された期限までに、郵送または窓口で書類を提出します。
- 審査・振込:自治体で書類の審査が行われ、問題がなければ指定の口座に給付金が振り込まれます。
- 振込までは、自治体の処理状況により数週間から1ヶ月程度かかる場合があります。
重要なポイント:DV被害など特別な事情がある場合は、現在住んでいる場所の自治体に申請できる場合があります。困ったときは、まずは自治体の窓口に相談しましょう。
ここで一度、あなたの状況を確認してみましょう。
あなたは住民税非課税世帯ですか?もしそうであれば、お住まいの自治体から給付金に関する通知が届いているか確認しましょう。
まだ届いていない場合や、内容が不明な場合は、すぐに自治体のウェブサイトをチェックするか、担当窓口に問い合わせてみてください。
迅速な対応が、給付金を確実に受け取る鍵となります。
今後どうなる?国民一律給付金の検討状況と全体の経済対策

この章でわかること
- 国民一律2万円給付金の現在の検討状況
- 検討されている給付金の対象者と支給額
- 支給時期が未定である理由
- 物価高対策としての政府の全体的な経済対策
国民一律2万円給付金は「検討段階」
石破首相は、テレビ番組などで国民一律の給付金について言及していますが、現時点(2025年9月)では、その導入は検討段階にあり、具体的な支給時期はまだ決まっていません。
報道では「1人あたり2万円」といった具体的な金額が取り沙汰されていますが、これもあくまで検討内容の一つであり、最終的に決定されたものではありません。
なぜ「検討段階」なのか?
国民一律の給付金は、住民税非課税世帯への給付金とは異なり、以下の理由から慎重な検討が続いています。
- 財源の問題:国民全員に給付する場合、莫大な財源が必要となります。その財源をどこから捻出するのかが大きな課題です。
- 経済効果の不確実性:国民一律で給付しても、貯蓄に回されて消費に繋がらない可能性や、物価をさらに押し上げてしまう「インフレ加速」のリスクも指摘されています。
- 公平性の問題:本当に困っている人への支援が手薄になる、といった公平性の観点からの議論もあります。
これらの議論を踏まえ、政府内では、国民一律給付金を実施するべきか、あるいはよりターゲットを絞った支援策を強化するべきか、引き続き議論が行われています。
支給時期は「未定」:早くても2025年度後半以降
国民一律2万円給付金が仮に決定されたとしても、その支給時期は早くても2025年度後半(2025年10月以降)以降になると見られています。
現在実施中の住民税非課税世帯への給付金ですら、自治体によっては手続きに時間がかかっている現状があります。
国民全員を対象とする大規模な給付となると、さらなる時間と準備が必要になるためです。
具体的な支給が決定した場合は、国から正式に発表され、各自治体を通じて国民に周知されます。
現時点では、この情報に一喜一憂せず、冷静に公式発表を待つことが重要です。
物価高対策としての政府の全体的な経済対策
国民一律給付金が検討段階である一方で、政府は物価高対策として、現金給付以外にも様々な経済対策を既に実施・検討しています。
例えば、
- 電気・ガス料金の負担軽減策:2024年度から引き続き、電気・ガス料金の一部を補助する対策が継続されています。
- 関税停止措置(検討中):一部の輸入品にかかる関税を一時的に停止または引き下げることで、物価そのものを抑える対策も検討されています。これにより、食料品や日用品の価格が下がり、家計の負担が間接的に軽減されることが期待されます。
- 賃上げの促進:企業への賃上げを促すための税制優遇や補助金などが実施されています。
政府はこれらの対策を組み合わせることで、国民の生活負担を軽減し、同時に経済全体の活性化を目指しています。
給付金は、こうした総合的な経済対策の中の、直接的な家計支援の一環として位置づけられています。
インフレに左右されないために自身の資産を運用しましょう!SBI証券でつみたてNISAを始めるなら以下の記事をご覧ください。↓
まとめ:給付金を賢く活用!最新情報と行動のすすめ

今回の記事で解説した給付金について、現時点(2025年9月)で特に重要なポイントを再確認しましょう。
- 住民税非課税世帯への3万円給付金は、既に実施が決定しており、多くの自治体で支給が始まっています。
- 対象となる可能性がある方は、お住まいの自治体からの通知を必ず確認してください。
- 通知が来ていない、または不明な場合は、自治体の窓口やウェブサイトで積極的に情報を収集しましょう。申請が必要な場合もあります。
- 18歳以下の子どもがいる場合は、追加で2万円が加算されることを忘れないでください。
- 国民一律の2万円給付金については、まだ検討段階であり、具体的な支給時期は未定です。
- 現時点では、この給付金が確実に実施される保証はありません。憶測や誤情報に惑わされないよう、国の公式発表を待ちましょう。
- 支給時期は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村のウェブサイトや広報で最新情報を確認することが最も確実です。
- 自治体のホームページには、専用の案内ページが設けられていることが多いです。
給付金は、あなたの家計を直接支援してくれる大切な制度です。申請が必要な場合は、期限を逃さずに手続きを完了させましょう。
また、不審な電話やメール、ウェブサイトには十分注意し、自治体を装った詐欺に巻き込まれないよう気を付けてください。
常に最新情報を確認し、賢く給付金を活用して、物価高に負けない家計づくりを目指しましょう。




コメント