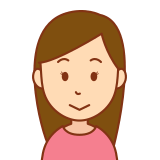
iDeCoとつみたてNISAって何が違うの?どっちをやったらいいの?
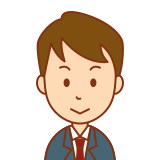
iDeCoとつみたてNISAは似てるようで全然違うものなんです。こな記事をしっかり読み込んで、自分に合った方を始めましょう!
iDeCoとは
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で積み立てて運用し、将来の年金を準備する私的年金制度です。運用益非課税や所得控除の優遇制度があり、効率的に老後年金を貯められます。
つみたてNISAとiDeCoの違い
| 項 目 | つみたてNISA | iDeCo |
| 目 的 | 中長期的な資産形成 | 老後の資金準備 |
| 運用時間 | 無期限 | 60歳まで |
| 年間投資上限額 | 360万円 | 2万円~6.8万円(職業による) |
| 対象商品 | 投資信託、ETF、株式、債券等 | 投資信託、定期預金、保険 |
| 税制優遇 | 運用益が非課税 | 運用益が非課税+所得控除 |
| 途中引き出し | いつでも可能 | 原則不可 |
絶対に引き出すことが出来ないというところをチャンスと捉えるのか、ネックと捉えるのかがカギですね。
iDeCoのメリット
積み立て時の所得控除
掛金が全額所得控除の対象となり、所得税と住民税を軽減できます。これにより、節税効果が大きく、特に高所得者ほど恩恵を受けやすいです。
運用益が非課税
通常、運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税となるため、効率的に資産を増やせます。
受け取り時の税制優遇
iDeCoは受け取り時に2種類の方法があります。年金形式なら「公的年金等控除」、一時金形式なら「退職所得控除」が適用され、税負担を軽減できます。
自由な運用商品選択
元本確保型(定期預金など)や投資信託など、自分のリスク許容度に応じて運用商品を選べます。
iDeCoのデメリット
60歳まで引き出さない
積み立てた資産は原則60歳まで引き出しができません。ライフイベントで急な資金が必要な場合には対応できないため、流動性が低い点がデメリットです。
途中解約が基本的に不可
中途脱退は特定の条件を満たした場合のみ可能で、単純に解約したい場合は認められません。しかしながら、掛金を減らすことは出来ます。最低月5,000円です。
価格変動リスク
投資信託などで運用する場合、価格変動リスクが伴います。元本割れの可能性もあるため、リスク許容度を考慮する必要があります。
手数料負担
加入時や運用中に手数料が発生します。これには国民年金基金連合会への手数料や運営管理機関への手数料などが含まれ、全て自己負担です。SBI証券を例にあげると3,000円です。
iDeCoの始め方
金融機関を選ぶ
- iDeCoを取り扱う金融機関(銀行や証券会社など)を選びます。
- 手数料や運用商品の種類を比較して、自分に合った金融機関を選択します
申込書類の取り寄せ
- 選んだ金融機関から「個人型年金加入申出書」などの必要書類を取り寄せます。
- 一部の金融機関ではWebで申し込みが可能です
必要書類を準備
- 基礎年金番号(年金手帳や通知書で確認)
- 本人確認書類の写し
- 掛金引き落とし用の銀行口座情報
- 事業主証明書(会社員で給与天引きを希望する場合)
運用商品を選ぶ
投資信託や定期預金など、リスク許容度に応じた運用商品を選びます
申込書類を提出
- 必要事項を記入し、添付書類とともに金融機関へ送付します。
- 書類不備があると手続きが遅れるため、慎重に確認します。
審査と口座開設
- 国民年金基金連合会での審査に1~2ヶ月かかります。
- 開設完了後、ログイン情報が郵送されます
掛金の積立開始
指定した口座から掛金が引き落とされ、運用がスタートします。
おすすめ証券口座について
結論からいうと、SBI証券か楽天証券です。理由は以下の5点です。
- 手数料が3,000円からと安い。
- 銀行や保険会社で始めると、そこに払う手数料が増える。
- ネットで簡単申し込みできる。
- 取り扱う商品が多い。
- 運用状況をネットで簡単に確認できる。
まとめ
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で積み立てて運用し、将来の年金を準備する私的年金制度です。運用益非課税や所得控除の優遇制度があり、効率的に老後年金を貯められます。つみたてNISAとは目的や年間限度上限、引き出し可能時期等が異なります。どちらを先にやるべきかしっかり考えましょう。
また、強力な税制優遇がある反面、途中で引き出せないというデメリットもありますので注意が必要です。
始めたい方はこの記事を参考にしてもらって、わからないことがあればお問い合わせで訪ねてください。



コメント